このように再婚によってまず第一に家庭生活に落ち着きを取り戻した教祖は、事業の再建に全力を尽くした。したがって実業家としての生活は表面的には変わることなく続けられたのである。しかし、家族との死別や事業の危機といった数々の切ない浮世の体験を経ることによって、その心中深く、大きな思想の転換が始まりかけていたのである。
教祖は物心ついてからこの時まで、終始一貫、神仏を否定して生きてきた。神社の神体も、仏像も、十字架もみな人が作った物であって、人間みずからの手になるものを人間が拝むなどということは不合理もはなはだしい。人生は自己の努力とオ能で切り開いていくものだというのがその持論であり、それが生活上の信念でもあった。すなわち、自分の可能性というものに絶対の自信を持ち、努力を重ね、人として正しい道を歩むならば、望んでかなわぬものはこの世にはないはずだと信じきってきたのである。しかし、この自信はもろくもくずれ去る時期が到来したのであった。
思えば、事業の破綻と妻子との死別というたび重なる深刻な不運は、さしもの教祖に、人の力のはかなさと、とうとうとして流れる運命の底知れない奥深さを、いやというほど、痛烈に思い知らさずにはおかなかった。それまでいだいていた人生観、世界観は一変し、無神論者であった教祖が、まったく別人のように、救いの道を求めて、さまざまな宗教の門を叩き、この悲運からの脱脚を真剣に考えるようになったのである。
そのころ、知人に天理教を信仰する人があり、また、親類に日蓮宗の寺の住職がいて、これらの宗教に入信することを勧められたが、どうしても心が向かなかった。
教祖が当時、ほかにどのような宗教に触れたかということについては、それ以上の記録がない。しかし後年になって河口慧海をたずねた経験について触れ、死後の世界など、心にかかるさまぎまな問題について問いかけたが、その答には、もうひとつ心を引くものがなく、そのままになってしまったと述べている。
河口慧海(一八六六年~一九四五年)は黄檗宗の僧侶で、仏教の経典を求めて単身チベットへ行くこと二回、厖大な資料を日本に持ち帰ったことで知られている。大正八、九年(一九一九、二〇年)のころは、上野に近い根津宮永町に住み、各地で講演会を開いたりしていたから、教祖がたずねたのはそのころではなかったろうか。
教祖が救いの道を求め、模索を続けていたその当時、東京にはさまぎまな宗教活動が行なわれていた。
大正七、八年(一九一八、九年)のころ、奇しくも河口慧海に師事していた臨済宗の師家山田無文が、そのころの東京神田付近の様を、つぎのように述べている。
「第一次大戦後の当時の東京は、社会運動も盛んであったが、精神運動もなかなか活発であった。神田辺*の夜を歩けば、どこかで救世軍が太鼓*たたき、仏教済世軍*がラッパを吹いていた。
湯島の麟祥院では、建長寺の菅原管長*が禅会**を持って提唱をしていたし、……富士見町の教会には、植村正久先生*がもっぱら学生の人気を集めておられ、内村鑑三*先生の下には、熱狂的な青年信徒がはせ参じた。……中央仏教会館へ行けば、毎晩欠かさずだれかの説教が聞かれた。
宗教花やかなりし時代ともいえよう。」(『手を合わせる』山田無文著・春秋社)
* 振り仮名は編集者・挿入
** 禅の講義
救いの道を求めていた教祖は、あるいはこうした集会に参加して、その説くところに耳を傾けたことがあったかもしれない。
教祖はたとえ商人ではあっても、すべてを損得で推し量る人間ではなかった。商人であるからには、利害、得失を無視することはなかったが、みずから正しいと信ずることのためには、どれほどの金も惜しまなかった。すでに触れたように、苦学生に学資を送ったのも、病に冒された女中への送金や救世畢への寄付も、すべてそうした心の現われであった。そして若いころから終始一貫、実行の人であっただけに、自分は可能な範囲でさまぎまな善行を積んできたという自負があったのである。それにもかかわらず、襲ってくる運命はあまりにも苛酷であった。
教祖はなぜ、そのような苦難が自分の身の上に集中して降りかかってくるのか、真剣に考えれば、考えるほど理解に苦しんだ。せめて信仰にはいって、この疑問を解き明かそう、それは可能ではないかと心の底から考えたのである。しかし、魂を引き付けられるような宗教に出会うことはなかなか叶わなかった。
このころ、新聞に大きく宣伝広告を載せ、全国各地で講演会を催すなど、積極的な布教活動を展開していたのは大本である。
教祖はある日、ふだんから、よく映画を見に行く神田の錦輝館で、大本の講演会が開かれたので聞きに行ったところ、強く心引かれるものがあった。度重なる苦難によって人生の意味を問い続けてきた教祖には、それは闇の中の光明に映り、これがきっかけとなって大本入信を決意したのである。大正九年(一九二〇年)六月のことであった。
大本は、明治二五年(一八九二年)、開祖・出口なおによって京都府綾部に開かれた宗教である。開祖のなおは、大正七年(一九一八年)、八二歳の生涯閉じたが、それまでの二五年間、半紙に筆をもって記した厖大な教えを残している。いわゆる『お筆先』であるが、そこに一貫するものは、艮の金神(一般には鬼門とされる東北にいる方位の神とされている)の出現により世の誤りが正され、やがて理想世界が実現するという、いわゆる「世の立替え、立直し」の思想である。『お筆先』には、こういう予言が独特の力強い言葉で、繰り返し述べられているのである。出口家の養子となった上田喜三郎、後の出口王仁三郎は『お筆先』を整理、体系化し、教団の組織も改めて、大本を全国的な大教団に発展させた実力者であり、信者は彼を聖師と呼んでいる。
大正八年(一九一九年)一〇月、その宣教の拠点が初めて東京に設けられた。四谷区南寺町の確信会がそれである。以後、東京における大本の布教活動はにわかに活発になり、翌大正九年(一九二〇年)の春からは、大学の講堂や映画館などを会場に、各所で講演会が開かれるようになった。教祖が開きに行った神田錦輝館の講演会も、そのなかの一つであった。
ところで、教祖が数多い宗教の中で、とくに大本に心引かれた理由は、第一に、その「世直し思想」にあった。『お筆先』には、「三千世界の大掃除・大洗濯」をして「万劫末代つづく神国の世にいたすぞよ」という、立替え、立直しの教えが随所に見られる。生まれつき、人並み以上に正義感が強く、政治家や特権階級の腐敗不正を見ると、憤激の念を禁じえなかった教祖は、悪のない世の中をつくるため新聞発行を思い立ち、その資金として一〇〇万円を作ろうと頑張ってきたのである。『お筆先』には、その理想とする正しい世の中を「これから神がつくるのである。」と、明記されている。この教えは教祖の心を強く揺さぶったのである。
教祖が大本に引かれた第二の理由は、薬毒に対するその教えであった。
教祖は幼いころから病弱で、医学を信頼し、医者と親類同様の付き合いをするほどであったが、その後、自分自身の歯痛の体験から、病を癒すはずの薬が、じつは病の原因になっているという、薬の恐ろしさを身をもって味わった。そして薬の毒性について深く覚るところがあったのである。それが大正三、四年(一九一四、五年)ごろのことであった。そして、この体験から数年後、自分のいだいていた信念が、『お筆先』の中にも記されているのを見て、意を強くしたのであった。
教祖は引き入れられるようにこの信仰の世界に没入した。そして入信早々から、店員たちにも勧めて修行のため綾部に行かせるほどの熱の入れ方であった。
こうして、家族や店員の中に何人かの信者ができたころ、予期もしない事件が起きた。それは、長い間、実のわが子同様に養育してきた甥・彦一郎が事故で死亡したことである。
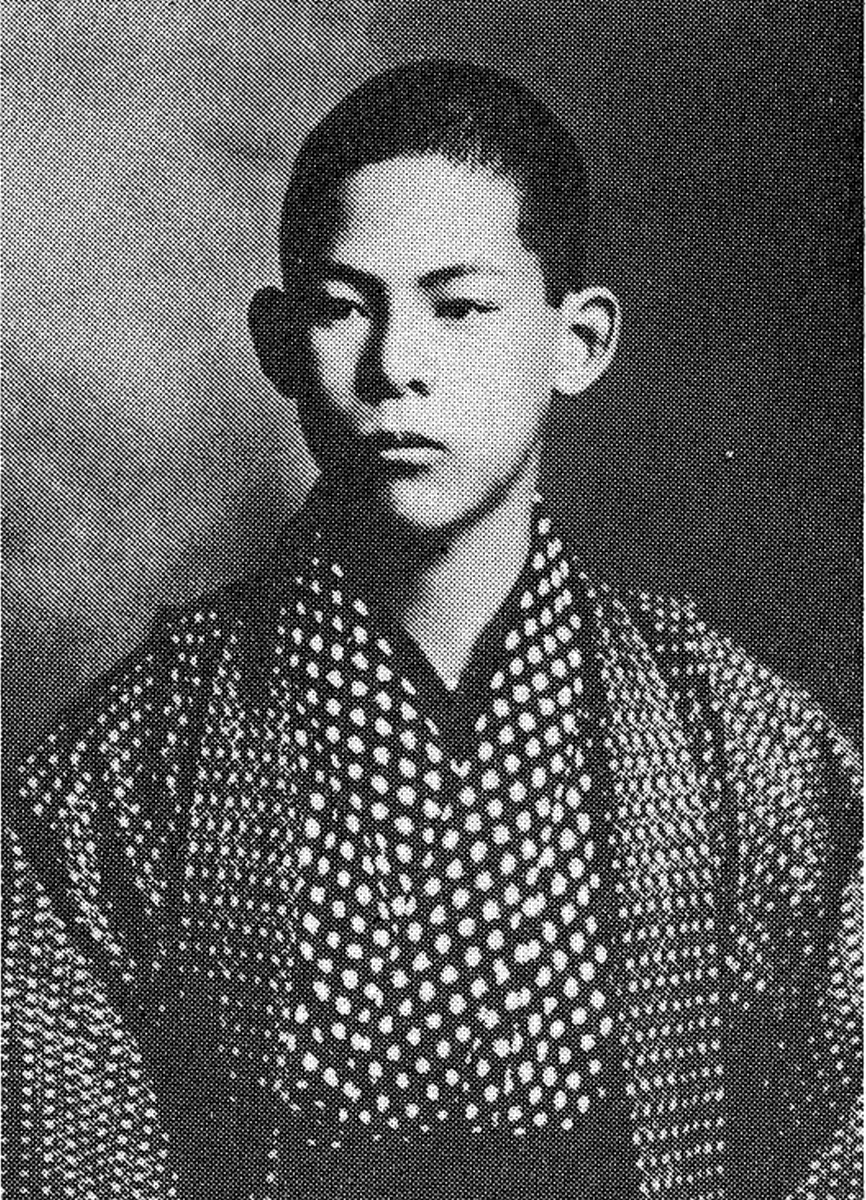
大正九年(一九二〇年)の夏、彦一郎は何人かの店員と綾部へ修行に行った。そして近くを流れる和知川で泳いでいる最中に、綾部井堰下というところで水死したのである。渦に巻き込まれた店員を助けようとして飛び込み、店員を救ったが、それと引き換えに自分は命を落としたのであった。彼はまだ二〇歳前の学生であった。
綾部へ修行に行っている間の出来事であり、とくに血を分けた息子のように可愛がっていた教祖には、大きな衝撃であり、深い悲しみであったに違いない。その思いは教祖の兄の武次郎も同じことで、甥を失った悲しみからその間接の原因となった信仰に怒りをぶつけ、「こんな信仰はやめてくれ。」と強く望んだのである。
やがて、事業再興の見込みがついたこともあり、彦一郎の事故死のあと、約三か年、教祖は大本から遠ざかった。しかし、見えざる世界に対して、ひとたび開かれた眼は、二度と曇ることはなかった。愛しい甥の死によって、ますます、見えざる力に動かされる人の運命というものを感じ取り、『お筆先』の研究や心霊研究など宗教の世界に深く分け入り、その学びを続けたのである。
元来、徹底した無神論者であったものが、この時期を境に有神論に変わったのであるから、正に一八〇度の大転換がなされたのであった。世にいう回心である。
教祖自身、神霊の世界に眼を開かれ、人生観の一変したこの時代を振り返って、「みずからの人生における第二の誕生であった。」と明言している。
