療術行為を許された教祖は、一年三か月の空白を取り戻すべく、懸命の努力を続けた。このころ、後に「日本観音数団」の管長となった渋井総斎(本名・総三郎)が入信している。渋井は明治一九年(一八八六年)、埼玉県北埼玉郡の生まれで、若くして上京し、洋服業を営んでいた。
当時は新宿駅の近くの角筈に大きな店を構え、「解脱会」という宗教団体の幹部であったが、近親者が浄霊によって救われたことから、中島一斎を知り、その紹介で昭和一二年(一九三七年)一一月に教祖の浄霊を受け、翌一三年(一九三八年)三月に入信したのである。渋井が初めて教祖に会った時、新旧一〇名ほどの信者がその場に居あわせたが、そのあとで教祖は井上茂登吉を呼んで、
「今日、初めて来た、肥った男の人はどういう人か。」
と尋ねた。初対面のことゆえ、井上はよくわからず十分な返事ができないでいると、重ねて、
「あの人は非常に頭のいい人だ。将来きっと役に立つよ。」
と言った。教祖のこの言葉は、数年のうちに現実のものとなったのである。そのころ、とくに渋井の心を強くとらえたことは、教祖の神格と、その唱えた夜昼転換の教えであったという。
やがて家業の洋服業は店員に任せ、自分は店の三階の六畳、四畳半の二間を浄霊室として神業に専従するにいたった。渋井は内に不屈の信念を秘めながら、温和な人柄と、人の心を引き付ける話しぶりで人々を魅了したが、何よりもその浄霊の力が著しく、奇蹟が相次いだので、大勢の人々が集まるようになり、三階だけではどうにもならず、二階の二部屋も解放する盛況であった。そのころ多い時には一日に一五〇人を越える人々に浄霊を取り次いだのである。
間もなく、茨城県水戸市にも出張するようになった。夕方まで三階で浄霊をしたあと、真夜中に水戸に着く列車で出かけ、着くとすぐ待っている人々に浄霊をして、朝の一番の列車で帰京し、自宅三階でまた浄霊を取り次ぐという、厳しい毎日が半年も続いた。そのころ睡眠時間は一日二、三時間、時間がなくて夕食を食べられないこともよくあったという。
このようにして、教線は目覚ましく伸展するようになり、当時、渋井の所で、浄霊や受付を手伝っていた人々の中から多くの人材が生まれ、「世界救世教」の柱石となって神業に奉仕したのである。
入信当時、渋井は近くの新宿柏木にあった持ち家二軒を処分して献金したが、さらに昭和一六年(一九四一年)、教祖が丹波・元伊勢<*>その他へ旅行した時にも、今度は杉並の方にあった家作(貸家)を売却してその費用にあてるなど、終始変わらず教祖のために熱心な奉仕を続けたのであった。
*京都府加佐郡大江町内宮にある皇大神杜。伊勢神宮に遷される前、天照大神を奉斎した吉佐宮と伝えられ、古来元伊勢大神宮と呼ばれ崇敬された社
布教を始めるようになってからの渋井は、接する人に好感を与えるようにと、鏡を見ては笑顔の稽古をしたり、相手に固苦しさを感じさせないように、あぐらをかく練習を重ねたりしたという。渋井が教祖の所へ面会に行く時は、いつも前掛けをして行ったことはよく知られているが、これについて自身つぎのように述べている。
「私は明主様にご面会の時には、和服に前掛けを掛けてうかがうことにしていました。このことは、はなはだか奇異な感じがするらしく、ある日、一人の信者から、『偉い方の前に出るというので掛けている前掛けをはずすのならわかりますが、先生はどうしてまた、わざわざ前掛けを掛けて、明主様の前にお出になるのですか。」と尋ねられました。それで私は『私はみなさんの先生であるかもしれないが、明主様から見れば、ただの小僧か丁稚にすぎない。私はこの気持ちをいつも忘れないようにしています。前掛け姿で明主様のみ前に出るのも、この気持ちの現われなのです。」と答えました。
また、昭和一七年(一九四二年)の夏、医薬問題から、私は一週間ほど留置されたことがあり、ひどい拷問も受けました。そのさい、明主様は、『いくら渋井でも、拷問には勝てないだろう。。」とご心配くださったそうですが、しかし、私は歯を食いしばって耐え、明主様のメの字も口にしませんでした。明主様のためなら、たとえ殺されても、というのが私の本心でした。」
次女のモト子は、当時のことを回想して言う。
「その時父は、『明主様は救い主なんだ。私は明主様のためなら獄死してもいい。お前たちもそのつもりでいなさい。」と言って警察へ行きました。父の並々ならぬ決意に大変強く打たれたことを、今でもはっきり覚えております。」
渋井は昭和三〇年(一九五五年)、教祖昇天三月後の五月一七日に六九歳をもって帰幽した。
昭和一二年(一九三七年)、療術行為が再開されて、当初、浄霊を受けに来た人は、日に一〇人前後であったものが、翌一三年(一九三八年)にはいると二〇人前後となり、しだいにふえて同年末には連日三、四〇名を数えるにいたっている。そうした中には教祖の浄霊を受け、奇蹟を体験して、太い神縁に結ばれた者が少なくなかった。
昭和一四年(一九三九年)の四月のこと、日本画家・岩松栄(後の「大愛教会」会長)の長女が、大腿部のカリエスと診断され、「即刻入院、少しでも動かしたら片足を付け根から切断しなければならなくなる。」と言われた。驚いた岩松は、かねてから世話になっていた渋井総斎に導かれ、翌日、さっそく病児を連れて宝山荘へ行った。教祖は、前に立っている子供に掌を近付け、半眼に見据えて一瞬息を殺し、祈るがごとく浄霊をしたが、その間約二分。岩松は、言い知れぬ尊厳の気に打たれ、厳粛な気持ちでかたわらに控えていた。そして、
「これでよし、もう治った。これでもう来なくていいですよ。」
と言う言葉に、はっと我れに返り、思わず畳に手をついて深々と頭を下げたのであった。けれども、そのあまりのあっけなさに、内心では教祖の言葉を信じかねた。しかし子供は正直なもので、そんな父の思いをよそに、来る時は痛みで足をつくこともできず、抱きかかえられてきたのに、帰りには先に立って部屋を出ると、玄関の方へ駆けて行くのであった。
このような大きな奇蹟を体験し、教祖への尊崇は不動のものになった。そのうえ「日独伊と米英が対決し戦争に到る。」という教祖の予言がしだいに事実となっていったことに深い感銘を受け、昭和一五年(一九四〇年)九月、入信と同時に専従の道にはいった。岩松は昭和二五年(一九五〇年)、教団本部の理事になるとともに、社会事業部長となり、その後も要職を歴任している。
岩松が初めて宝山荘をたずねたと同じ昭和一四年(一九三九年)の秋、東京の鉄鋼業界の老舗である木下商店に勤める箕浦二郎(後の「光風教会」、及び「晴光教会」会長)は、生来の病弱な体質に無理が重なって神経衰弱になり、そのうえ、妻や子供の健康もすぐれず、家族をあげて病院通いをしていた。この様子を見かねた友人が中島一斎を紹介してくれたのである。
一度の浄霊で非常に気持ちの良くなった箕浦は、さっそく入信を希望し、宝山荘の教祖のもとで一週間の講習を受けた。当時のお守りには「治病観音力」という文字が書かれていた。
入信後間もなく、箕浦の長女が猩紅熱にかかったので、義兄で真言宗の僧侶である高頭信正(後の「生和教会」会長)の寺(東京赤羽の真光寺)に寝かせ、中島一斎を招いた。すると一時間もしないうちに大変な奇蹟が起こった。一面に出ていた発疹が見る見るうちに乾いて粉のようになり、あとかたもなく消えてしまったのである。そして、それと同時に熟も下がり、どんよりとした目が生き生きしてきて、食べ物を欲しがりだしたのであった。
この奇蹟を目のあたりにした高頭は、自分の慢性盲腸が全快したこともあって、その秋に入信した。高頭は、教祖のきわめて柔らかな言葉使いや物腰と、しかも半面、厳として冒し難いその気品にすっかり魅せられてしまった。また、いろいろな質問に対し快刀乱麻を断つ即答ぶりに、それまでひとかどの宗教者を自負していたうぬぼれも消え、心からの帰依の思いがわいてくるのであった。高頭は入信と同時に浄霊を取り次いだが、奇蹟の続出に人々が殺到するようになったので、寺を治療所として翌一五年(一九四〇年)四月から専従の道にはいった。続いて義弟の箕浦もその年の六月に専従した。高頭は昭和四九年(一九七四年)一一月一一日、享年六九歳で、箕浦は昭和五三年(一九七八年)四月一四日、享年七五歳で帰幽したのである。
また、高頭の従兄弟の小林秀二(本名・庫二郎、後の「明成教会」会長)は、神奈川県平塚市で生命保険会社の支店長をしていたが、高頭らの話を信じるどころか、勝気な気性から、
「本元へ乗り込んで、インチキ療法の化けの皮をはいでやろう。」
と、勢い込んで教祖をたずねた。しかし、宝山荘へ通うこと三日三晩、ついに教祖の前に頭を下げ、昭和一五年(一九四〇年)五月に入信したのであった。そのうえ、
「あんたは曇りが多いから、人肋けをして徳を積まなければ、畳の上では死ねない。」と言う教祖の率直な言葉も、素直に受け止められるまでに心酔し、その後すべてを捨てて教祖に従い、神業に専念していくことになったのである。この小林は昭和二八年(一九五三年)一二月一九日に帰幽した。享年五五歳であった。
さらに同じ年の七月には、堀内照子(後の「照明教会」会長)と平本直子(後の「光の道教会」会長)が入信している。
照子は山梨県に生まれ、後に海軍中将となった堀内茂礼に嫁いだが健康を害し、ついに腸結核となり、医師にも見放されるにいたった。その時、隣りに住む、当時海軍大佐・野々山早吉の妻・貴恵に教えられて宝山荘へ行った。この時、教祖からつぎのように言われたのである。
「あんたの肉体がもつかどうかわからない。もし、あんたが浄霊を受けて死んだなどと新聞に出たら、他の多くの人たちが救われなくなる。あんた一人の命よりも、沢山の人たちの命の方が大切だから、私は断わる。」
突き放すようなこの言葉は、かえって堀内の心の眼を開いた。教祖の言葉の奥にひそむ大きな愛に打たれた堀内は、死んでも新聞に出さないことを約束し、宝山荘へ通い始めた。そのかいがあって日一日と快方に向かい、間もなく全快したのであった。その後、紹介者の野々山夫妻とともに、軍人や政治家、皇族の間に教祖の教えを広め、浄霊を取り次いで多くの人を入信に導いた。
堀内は一時は医師に見放された身体ではあったが、神業に専念し、入信四〇年目の昭和五五年(一九八〇年)一一月一日、八〇歳の天寿を全うして帰幽したのである。
昭和一五年(一九四〇年)七月、たまたま堀内が宝山荘で講習(後の入信教修)を受けている最中、幼児を抱きかかえた一人の母親が半狂乱の体で教祖の前へ通されてきた。神奈川県高座郡上溝(現在・相模原市上溝)に住む平本直子である。子供は三歳になる長女の千代子で、その朝から嘔吐を繰り返し、苦しみだしたのである。疫痢と直感した平本は、取るものも取りあえず、寝巻のままの娘をかかえ、宝山荘へ駆けつけたのである。以前、長男の脳膜炎を救われた平本にとって、すがる先は教祖以外になかった。幼児はもう死んだも同様で、目は固く閉じ、身体も冷たくなり、呼吸も感じられないほどであった。教祖は一目見るなり、
「連れてくる所が違う。」
と言ったが、平本は無我夢中で、
「困った時にはいつでも来なさいとおっしゃったじゃありませんか。」と叫んで子供を教祖の前に差し出した。教祖は、取り乱している平本をとがめることもなく、素早く羽織を脱ぎ、ぐったりと横たわっている女児に無言のまま手をかざした。そして、今度は片肌脱ぎになり、
「うむっ。」
と息を詰めて、浄霊を続けた。その間二〇分ほどであったという。やがて子供は目をあけ、
「おかあちゃん、おかあちゃん。」
と言いながら起き上がり、母親の胸に抱きついてニコニコと笑顔を見せた。平本はあまりのうれしさに声をあげてその場に泣きくずれてしまった。
それを見て教祖は共に喜び、
「ここでこの子に死なれたら私が困るからね。もう少し遅かったらだめだったよ。」
と言って、おいしそうに煙草を一服吹かしたのであった。
この噂<うわさ>を聞いた平本の家の近所の人が平本から浄霊を受けるようになり、ここでも大きな奇蹟が生まれ、連日大勢の人々が浄霊を受けに来るようになったのである。
その年の一一月二三日のことである。平本が宝山荘に行くと教祖がいつになく、
「私はもう浄霊をやめるんだ。これからはあなたたちが大いにやるんだから毎日来なさい。いろいろと教えてあげる。」
と言った。教祖が医師法違反容疑で玉川警察署に留置されたのは一一月二八日のことであるから、教祖はその五日前に、警察当局による弾圧を察知していたのである。
平本は翌、昭和一六年(一九四一年)四月、専従した。そのおり教祖に、布教にあたっての心構えを尋ねたところ、「寝食を忘れて人を肋けなさい。」、「恩は着るべし着せるべからず。」、「何事も私(教祖)と共同作業である。」という三点を教えられた。それ以来この言葉を信条として布教に挺身したのである。さらに、このことがあってから四か月後の八月、平本は教祖の命を受けて、幼い子供二人をかかえた女の身で、生まれ育った土地を離れ、遠く本州西端の山口県、萩へ布教に旅立った。その心を支えていたものは、ただ教祖に対する絶対帰依の心であった。
生物学を専攻した学才の士であり、熱心なクリスチャンでもあった稲川栄一は、子供のころから喘息を病み、西洋医学はもちろん、漢方、鍼灸といろいろ手を尽くしたがよならず、十数年にわたって苦しんでいた。
昭和二六年(一九四一年)に、たまたま知人の勧めで浄霊を受けたところ、今まで経験したことのない爽快感に驚喜し、さっそく、中島一斎のもとで入信、やがてキリスト教の信仰も、中学教師の職も捨てて専従の道にはいったのである。
その後も喘息の発作は続いたが、そのたびに玉川・宝山荘に泊まり込み、教祖直々の浄霊を受ける機会に恵まれた。当時のことを、
「有難いことに、私は大先生(教祖)のご治療(浄霊)を何度もいただきました。夜でも発作のひどい時にお願いして、お部屋にうかがいますと、大先生は観音様のお姿を描いていらっしゃることがよくありましたが、そんな時、描きかけのお絵をちょっとずらして治療をしてくださったのでした。余談ですが、大先生が観音様のお姿をお描きになる時は、一〇体をひとまとめに描画を進められました。ですから、できあがる時は、一〇体が一度に完成というわけです。
発作が治まると、宝山荘の造園や自然農法のお手伝いをさせていただき、元気になると、またふたたび東京市内を中心に、治療や講習に飛び回っておりました。」
と語ったが、稲川は上流階級やインテリ層に多くの信者をつくり、後に「青光会」の会長となった。井上の『日記』には昭和一九年(一九四四年)二月四日に作家・吉川英治を、また同年三月と四月には陸軍予科士官学校の教官グループを教祖の所へ案内した記録が残っている。しかし、惜しいことに稲川は三三歳という若さで、昭和二二年(一九四七年)六月二二日、帰幽した。
後に「日本教会」会長となった二本木暉子が新宿の渋井の治療院でお守りを受けたのは、昭和一六年(一九四一年)の一一月のことである。二本木はカリエスのため身動きもならず、死を待つばかりだったところを救われたのである。お守りを渡した渋井でさえ、二本木の状態を初めて見た時、余命いくばくもないと思ったほどの重病であった。
しかし、翌一七年(一九四二年)宝山荘で初めて教祖の浄霊を受けた時、二本木はいわば命の継ぎ足しをしてもらったと感じとった。教祖は、脇腹に沢山の膿がたまっているのを見て、
「これはひどい、口があいて出るか、小水になって出るかだが、小水で出るといいんだがな。」
とひとこと言った。するとその後、口があくこともなく、知らず知らずの間に取れてしまったのである。この奇蹟は横須賀方面に教祖の教えが大きく広がる端緒となった。二本木は教祖に救われ、以来、布教に挺身し、昭和四八年(一九七三年)八月二八日、享年六二歳で帰幽した。
このようにして教祖に救われた人々の中からは、今度は自分の方から少しでもその受けた大恩に報い、すばらしい神力を取り次いで人肋けをしたいと専従の道に踏み切るものが、日に月にふえていった。もとより、民間療法として許可を受けていたとはいっても、教祖と同様、官憲の警戒、監視は厳しく、いつ検挙されるかもしれない緊張の中で布教は続けられたのである。
しかし奇蹟は相次ぎ、多くの人が浄霊を求めて集まり、教祖の徳を慕う人々は急速にふえていったのである。
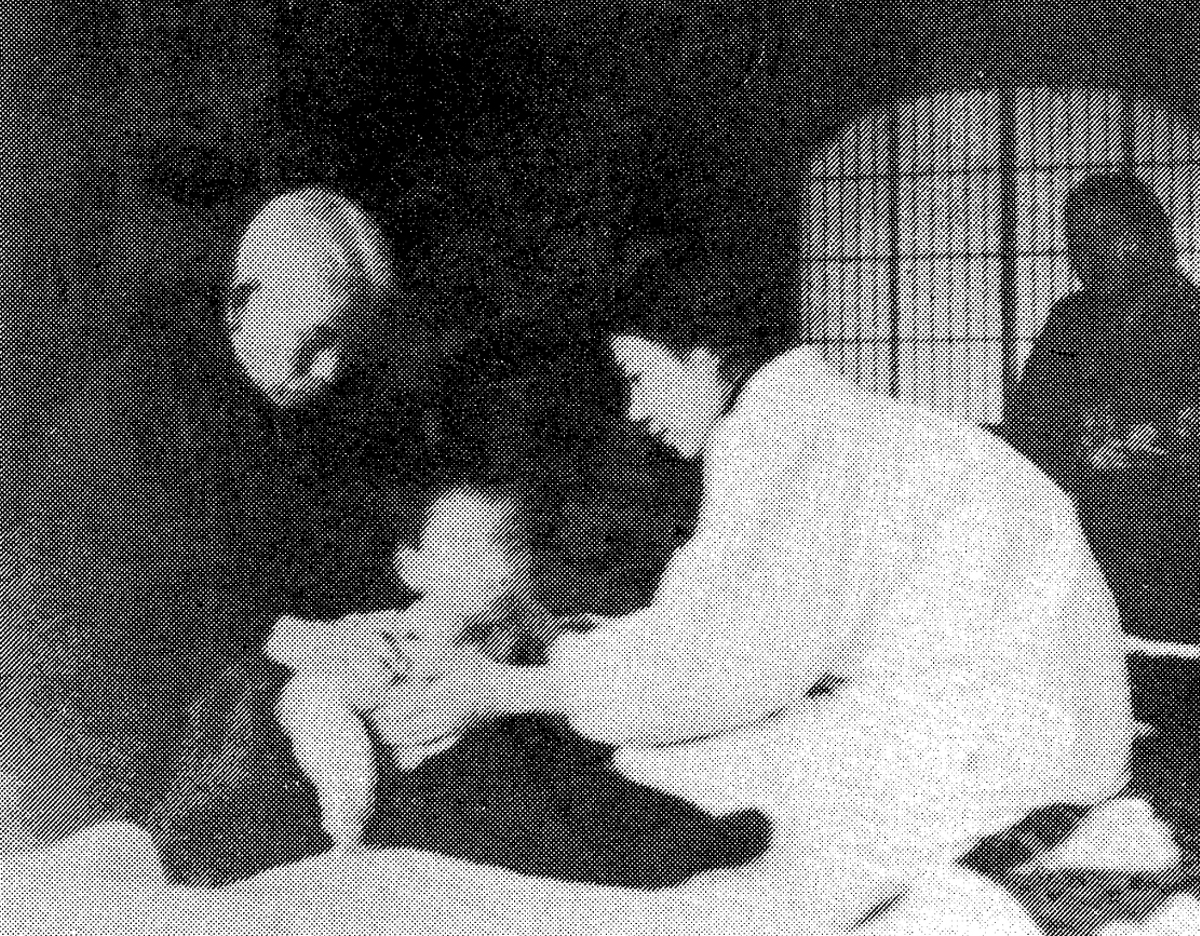
奇蹟の療術として、もっとも隆盛を極めたのは、昭和一五年(一九四〇年)の夏から秋のことである。来訪者はまず受付係の井上から番号札を受け取り、順番を待つ。やがて別室で弟子から浄霊を受け、それから教祖の浄霊を受けるのである。教祖は訪れる人の分け隔てをせず、一視同仁で、地位や身なりで人を判断することもなかったから、おのずから尊敬と敬慕の念が集まったといわれる。発展の理由の一つにはそうした人柄と、周囲を包む温かな雰囲気にあったといえるであろう。
そのころの教祖の日常は毎朝七時ごろ起床して朝食をとると、決まって手に鋏を持ち、庭を歩いて草花などを採ってくる。そして別棟になっている自宅から浄霊室へ行き、観音像の掛けてある床の間に花を生ける。それから浄霊が始まる。午後の三時には茶菓子を食べ、茶を飲むだけで昼食はとらず、夕方の六時半から七時ごろまで浄霊を続けるのであった。
浄霊が済むと入浴して夕食となる。さらに夜の一〇時ごろからは「光明」の揮毫や、お<ゝ>ひ<ゝ>ね<ゝ>り<ゝ>(上巻三六三頁参照)作りが続けられるのであった。
しかしこのような霊・肉両面にわたる激務から教祖は日一日と目に見えて疲労の色が濃くなっていった。よ志はかたわらから見ていて内心心配でならなかった。ある日の夕方、富士見亭に帰った教祖は、酒を飲んで疲れを癒そうとしたが、猪口に一杯の酒を飲むか飲まないうちに顔面蒼白となり、脳貧血を起こして倒れたことさえあったのである。
