昭和五年(一九三〇年)は、日本の社会が長い不況の幕開けを迎えた多難な年であった。昭和四年(一九二九年)一一月の、アメリカ・ニューヨーク市の金融市場の中心地であるウォール街で起こった株の大暴落は、当時の人々の記憶に生々しく残っていた。農産物をはじめ、物価が下落し、生産が落ち込んで失業者が町にあふれるといった、暗澹とした年になったのである。
しかし、昭和五年(一九三〇年)の正月は、こうした世情にもかかわらず、毎日良い日和の天気が続いて明け方の冷え込みは厳しく、真白な霜柱が立った。教祖は、神業の発展を期し、決意と希望に満ちてこの新年を迎えたのである。とくに、この年は午年で、四八歳の教祖の干支*にあたっていた。
*干支は十干〈かん〉と十二支を組み合わして六〇配としたもので、これを暦の上の
年・月・日にあてはめて用いた
此年は神業とみに進む可く何とはなしに心勇むも
吾が身魂続く限りは神の為世の為救いの神業いそしむ
元旦には、例年と同様に番頭の福本と長島が店員を連れて挨拶に来た。また、麹町の正木三雄も挨拶に来ている。
翌二日は大森で月次祭があり、一八人の信者が参拝した。教祖は、墨で半紙に観音像を二枚描いて信者に与えた。それまで富士などの絵を描くことはあっても、観音の絵姿を描くことはこの日が初めてであった。さらに一月六日には、
内山の母の熱心に動かされ我が御手代を与へけるかな
という歌が記されている。
御手代というのは古く御手座代〈みてぐらしろ〉と言われる言葉に相当し、御幣を手に持つこと、あるいは単に御幣そのものを意味した。しかし、大本では手に代わるもの、という意味に取り、杓文字〈しやもじ〉に出口王仁三郎が、
萬有の生命をすくう此釈子心のままに世人救へよ
などと書いて拇印をおしたものである。これを病める人々の救いに用いたのである。

これに対し、教祖が与えた御手代は扇であった。扇面の表に、
「万霊を浄めて救ふ此扇」
「万有の霊体浄むる此扇」
「身も魂も清むる白きこの扇」
などと書いて、おもだった信者に与え、鎮魂にあたらせたのである。
教祖がみずから御手代を揮毫して与えた最初の記録は、昭和四年(一九二九年)四月三〇日に見られる。この日の『日記』にはつぎのような記事がある。
山室氏御手代呉れと白扇を出せば吾れは句をば書きけり
そして同じ年の八月一二日には、
吾遣りし扇子の放つ霊光の輝き見ゆると山室語れり
と、御手代にまつわる奇蹟が記されている。こうして昭和元年(一九二六年)の啓示以来、独自の境地を極めてきた教祖は、昭和四年(一九二九年)から、それを具体的な神業として現わし、翌五年(一九三〇年)にいたって一層明確な一歩を踏み出していくのである。しかし、神業が着々と新しい歩みを進めていく一方で、店の景気はかつての繁栄に比べ今昔の感が深く、縮小の一途をたどっていた。教祖がしだいに信仰一本に打ち込んでいく一方で、非常な不景気が岡田商店を圧迫したのである。一月四日の『日記』に、
今日の日に初めて店へ赴けば小僧淋しく留守居してあり
今や人救いに命を捧げて、充実した日々を送っている教祖ではあるが、数十人の店員が忙しそうに立ち働き、「旭ダイヤ」が作るはしから飛ぶように売れていった、かつての黄金時代が、ふと脳裏をかすめたことであろう。がらんとした店で、一人ぽつねんと留守居をしている若い店員の姿には、実業家として生きてきた教祖自身の郷愁が重ね合わされている。
ともあれ、昭和四年(一九二九年)から五年(一九三〇年)の春にかけて、宗教家の道に徹〈てつ〉
しようとする心の一隅に、まだ赤い残り火のように実業家への情熱が感じられるのである。
生業を復び昔日(せきじつ)の其の如く花咲かせんと切りに思ふも
口すぎの生業なりと思ひしも神業の経綸型〈しぐみかた〉にてありき
日曜日にも関わらず店へ行き下絵の訂正ひとりなしける
昭和四年(一九二九年)の暮れから五年(一九三〇年)の正月にかけて、岡田商店への愛着を『日記』に書き留めた教祖であったが、その後次々と起こってくる神秘によって、しだいに神業一筋に立ちゆく日の近いことを予感するようになる。このころの『日記』には、霊感の訪れを伝える記事が数多く見られる。
天地に秘〈かく〉せる謎も時の来て奇しくも解くる事のうれしも
大神業進むを諸の出来事に悟りて胸の躍りけるかな
予期の如写真撮影の其際に深き神秘の現れありしも
こうした歌の中で、とくに注目されるのは、二月八日のつぎの一首である。
今年〈このとし〉の六月吾に大便命下る予感の頻〈しき〉りに来るも
腹中に秘められた光の玉が、日に日に充実し、みずからを通じて働く観世音菩薩の救済力がいよいよその霊徳を加えていく、そういう自覚に立ったのがこの歌である。
教祖は、来たるべき六月に思いをひそめた時、そこに不思議な数の重なりを見出した。それは六月一日が旧暦の五年(一九三〇年)五月五日にあたり、しかもその干支が、午〈うま〉の年の、午の月の、午の日になるという事実である。このように数字と干支がそろうということはきわめてまれである。教祖は、この奇しき日こそ、二月の予感に示された日であり、この日を期して神力の新たな躍動が始まると感じとった。そしていよいよ六月一日になると、かねてから用意していた十三重の石塔(「みろく塔」と名付けた)を庭の一隅に建立し、ひそやかな祝いをしたのである。教祖は、その日、一日中、絶え間なく喜びが胸に込み上げ、心がはずみ、神から下されたみずからの使命に向かっての新たな勇気がわいてくるのを禁じえなかった。
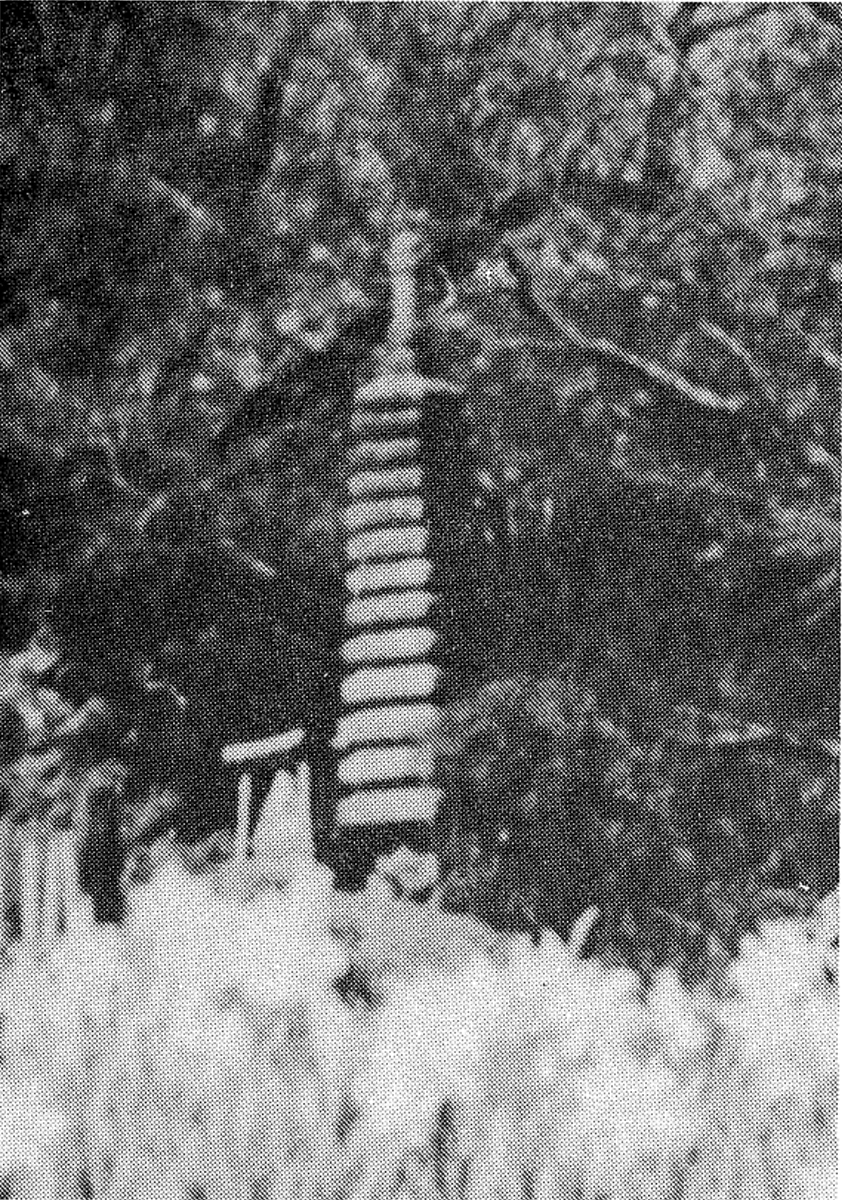
そしてこのころ、光の玉の霊力の高まりを教祖自身が自身するうえで重要な奇蹟が生まれている。それは、花街の女と情死しようとしていた青年を、鎮魂によって救った時のことである。その青年を自宅に伴い霊査をしてみると、狐霊が憑依していることがわかった。そこで狐に戒告与えて離脱させた。しかし青年はなおれである。教祖は、この奇しき日こそ、二月の予感に示された日であり、この日を期して神力の新たな躍動が始まると感じとった。そしていよいよ六月一日になると、かねてから用意していた十三重の石塔(「みろく塔」と名付けた)を庭の一隅に建立し、ひそやかな祝いをしたのである。教祖は、その日、一日中、絶え間なく喜びが胸に込み上げ、心がはずみ、神から下されたみずからの使命に向かっての新たな勇気がわいてくるのを禁じえなかった。
そしてこのころ、光の玉の霊力の高まりを教祖自身が自覚するうえで重要な奇蹟が生まれている。それは、花街の女と情死しようとしていた青年を、鎮魂によって救った時のことである。その青年を自宅に伴い霊査をしてみると、狐霊〈これい〉が憑依〈ひようい〉していることがわかった。そこで狐に戒告を与えて離脱させた。しかし青年はなおも瞑目合掌して動かない。数分たった後、青年はようやく目を開き、けげんそうな顔をして、今しがた不思議な光景を見たと言ってつぎのような話をしだした。
琴のような音楽を演奏している人物がおり、その音色〈ねいろ〉に耳を奪われながら、なお注意してよく見てみると、自分は広い神殿のような建物の中にいる。すると、教祖が衣冠束帯(正式の装束)に冠をかぶり、腰帯を付けた神官の服装)の姿で、静かに歩を運びながら階段を昇って御簾(神前にかけられたすだれ)の中にはいったというのである。教祖が、「後ろから見たのでは誰だかわからないではないか。」
と問うと、青年は確信に満ちた様子で、
「いえ、先生に間違いない。」と言った。青年が坐っている左側には神床〈かんどこ〉があることから、教祖は青年が一時的ではあったが、確かに霊眠が開けたものと受け止めたのであった。
昭和五年(一九三〇年)六月一日の神事から一か月余を経た、七月二一日のこと、教祖は妻のよ志ら一一名を伴って富士登山に向かった。
重大な神業なりける富士登山なさんと午前九時に家出づ
当日は薄く雲がかかっていたが、ときおり、陽の差すまずまずの天気であった。一行は、午後一時ごろ、中央線大月駅へ到着し、そこからバスで山中湖を経て河口湖の船津ホテルに投宿した。
河口の湖畔の岩に腰かけて黄昏るる迄涼みけるかな
翌日は西湖、精進湖、本栖湖を経て浅間神社に参拝、午後一時に富士吉田口から登り始めた。
よ志は教祖と同様に馬で五合目まで登ったが山酔いが激しく、やむをえず須走口へ下りた。
かくて、随行者は一〇名となり、さらに七合目まで登って石室*に一泊した。
*登山者用の宿泊施設。風あたりが強い所にあるため、山の斜面を背にして三方を石で積み上げた建物。中は土間に板を敷き、むしろをのべてある
翌朝三時半に出発、八合目で御来光〈ごらいこう〉を拝し、七時半には無事頂上に到着したのであった。

ところで、以前、教祖に龍神が憑って、
「自分は富士山に鎮まりいます木之花咲爺姫命〈このはなさくやのひめのみこと〉の守護神であって久須志〈くすし〉の宮に鎮まりいる九頭龍権現である。」と告げたことがあった。この宮をたずね、参拝することもこの時の登山の目的の一つであった。
教祖は当初、龍神から聞いた社〈やしろ〉は富士の山麓にあると思い、聞いてみたがわからなかったので、ひとまず富士山頂をめざしたのである。ところが山頂の入口近くに相当立派な神社がある。
見ると久須志神社(久須志は「くすし」。あやしく不思議なことの意を表わす)と書いてある。
それは、浅間神社の奥宮(奥社ともいう。同一の祭神を祀った本社・本宮より奥の方に位置する社のこと)で、別名を久須志神社ということがわかった。一行は神社に参拝を済ませると、登山の目的を達したので、お鉢めぐり(頂上を一周すること)の後、須走口から下山した。
さて大森の松風荘へ帰ってからのことである。随行者の一人が、不思議にも松風荘の洋間のソファーに腰かけた一八歳ほどの美しい女神を霊眼で拝したのである。頭髪に飾りを付け、麗しい十二単衣を着た、えも言われぬ気品の高い優美な姿であった。信者たちはその話を聞いて、麗しいその女神こそ、ほかならぬ浅間神社の祭神、木之花咲爺姫命であり、教祖一行の登山を喜んでお礼に訪れたのではないかと噂しあったのであった。
その数か月後、商売から全面的に身を引き、神業一途に没頭する決心を促す出来事が起きた。
それは松風荘のある新井宿の隣り町、馬込に住む桜木という一家にまつわる神秘であった。
桜木は印刷会社に勤める男で、一家をあげて熱心な信仰をしていた。
昭和五年(一九三〇年) 二有六日、午前三時ごろのことである。七歳になる桜木の娘弥生が腹痛で苦しんでいるので来てもらいたいと電話があり、教祖はさっそく同家へおもむいた。ところが不思議なことに、子供の病状は出産時の陣痛そのままで、しばらく痛みが断続したあと、やがて何かが生まれ落ちる気配があって、苦痛はおさまった。
病室へはいった時、教祖は、部屋の隅の箪笥の上に安置された一寸八分(約五・五センチメートル)くらいの観音像が目に付いた。戦国時代に武士が戦場に行く時、守り仏として腕へ巻きつけたもので、同家に古くから伝えられたものということであった。
朝方帰宅してから、娘が全快したという電話があったが、そのあとしきりに牛乳が飲みたくなったので、教祖は一杯の牛乳を飲んだ。
こうして早朝来の事柄を思い返すうち、この一連の出来事は、観世音菩薩がこの世に誕生した証しである事を感じとったのである。そして、午後になって訪れた桜木に、「弥生ちゃんは観音様を生んだんですよ。」と説明し、『日記』には、
暁の六時に家へ帰り来ぬ重大神業遂げし今日かな
と記したのである。この神秘な仕組によって、教祖は、みずからの腹中にある光の玉がしだいに輝きを増し、偉大なる霊格へと高められていることを自覚し、いよいよ事業を整理する決意を固めていくのである。
この年の一二月二三日、人類救済の神業に専念する日の間近いことを知った教祖は、初めて誕生の祝いをし、色紙に和歌を書いて、訪れた信者たちに与えた。それは教祖四八歳の誕生日であった。
吾誕生満四十八歳の今日の日の紀念を兼ねて御祭をなせり
